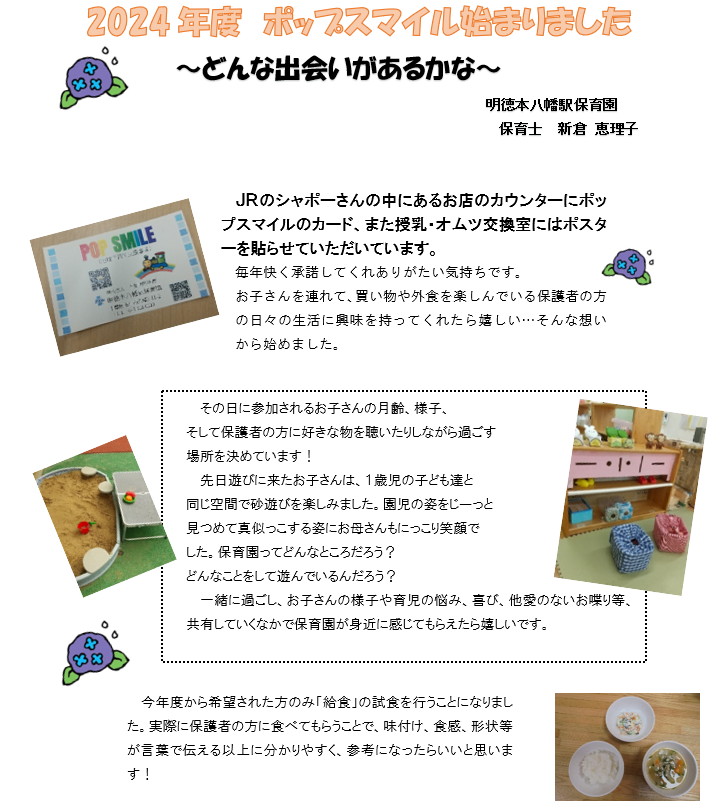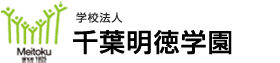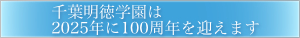学園ニュース
学園ニュース 2024年6月号(285号)
【中学校】

■◆■千葉明徳中学校 教諭 松田 真生子■◆■
6月12日(水)〜6月14日(金)、中学2学年は初めての宿泊行事である林間学校へ行ってきました。
事前に5月のうちから3回にわたって事前学習を行い、主な来訪先である足尾銅山と尾瀬ヶ原について、歴史や自然保全の意義を少しは理解してもらえたのではないかと思います。
1日目は足尾銅山の見学および植林体験を行いました。銅山見学ではトロッコに乗ったり、坑道を歩きながら展示を見学しました。暗くひんやりした坑道内には当時の採掘作業の様子がリアルに再現されており、かなりの重労働であったことが、生徒たちにもよくわかったようです。植林体験では、公害により失われた自然を取り戻す作業として、1人1本、木の苗を植えました。
2日目は本州最大の湿原である尾瀬ヶ原のハイキングに出かけました。今年度は大多数の中2生が、15km以上を歩く一番長いコースにエントリーしました。最初は歩ききれるか不安がっている子が多かったですが、晴天に恵まれ、初夏の美しい景色を存分に楽しむことができたようです。ガイドさんの説明を聞きながら、尾瀬の自然を実際に見て学びました。最後は全員、自分の足で戻ってくることができ、とても達成感があったと話していました。
3日目は吹割の滝周辺の散策および原田農園でのさくらんぼ狩りを行いました。岩が侵食によって削られたところにできた滝は、えぐられた地面に水が落ちていくような、不思議で雄大な光景をつくっていました。さくらんぼ狩りでは、生徒たちがまるで宝探しのように、赤い実を探して楽しそうに食べていました。
全日通して天候に恵まれ、生徒たちが楽しそうにしていたのが印象に残っています。学友と長い時間を共に過ごし、普段の生活ではできない経験をたくさん味わったと思います。共同生活の難しさや、自分に足りないものも見えたと思いますので、これからの学校生活に活かしてくれることを願っています。

▲
【短大】

■◆■千葉明徳短期大学 准教授 中嶋 一郎■◆■
2024年5月26日(日)、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場で毎年開催されている千葉県障がい者スポーツ大会に、本学の1年生84名と2年生2名、計86名がボランティアとして参加しました。
本学では「体験から学ぶ」という学習方法を重視しており、この大会も授業の一環として位置付けられています。学生たちは、さまざまな特徴を持つ人たちとの関わりを通じて、自己理解、他者理解、障がいの理解を深めることを目的に、毎年1年生がボランティアとして参加しています。
大会では、50m走、100m走、200m走、400m走などのトラック競技、立幅跳び、走幅跳びなどの跳躍競技、砲丸投げ、ジャベリックスローなどの投てき競技が行われました。学生たちは、競技への誘導、種目ごとの記録の掲示、受付業務などの役割に分かれてボランティア活動を行いました。
当日は5月とは思えないような暑さ(最高気温25.2℃)で、夏のような日差しが降り注ぐ中、競技者たちは日ごろの努力を結果に結びつけようと一生懸命にスポーツに取り組んでいました。学生たちも、ボランティアを通じて選手たちと関わる中で、多くの変化が見られました。
初めての経験に不安を抱いていた学生も少なくありませんでしたが、真剣に競技に打ち込む選手の姿や、競技中に必要なサポートをする人々、そして競技者を応援する人々の姿に感動し、実際にサポートを行う中で不安は次第に消えていきました。
また、学生たちは後日の振り返りの際に、国際生活機能分類に基づく障がいの理解が深まったことを示しました。今回のボランティア活動を通じて、学生たちは「障がい」に対する概念を見直し、理解を深めることができました。
来年度もこの大会を通じて、さまざまな人と関わり、学生たちが自己および他者の理解を深める機会となることを期待しています。

▲
【高校】

■◆■千葉明徳高等学校 教諭 林 直樹■◆■
高等学校中高一貫コースでは、今年度より6月上旬に「一貫進路の日」を設定しました。
この進路の日は、昨年度まで一貫コースの「全校遠足」で実施していたものを、別日程に再設定したものです。この行事は、最先端の研究所や首都圏の大学見学を通して、文系・理系問わず、生徒の進路意識を高めることが目的です。
今年度は、高校1年生(4年生)が、かずさDNA研究所(午前)と神田外語大学(午後)に、高校2年生(5年生)が、東京大学柏キャンパス(午前)と生徒各自の都内私大見学(午後)にそれぞれ向かいました。
4年生が訪れたかずさDNA研究所では、ブロッコリーからDNAを抽出する実験を体験し、研究所内の見学も行いました。また、神田外語大学では、大学教員から「大学で外国語を学ぶ意味」についての講義を受け、大学生によるキャンパス見学を行いました。中学時代のフィールドワーク中心だった「校外理科研修」からの大きな変化を体験できたと思います。
一方、5年生が訪れた東大柏キャンパスでは、最初に大学教員による「海洋学者という進路を選んで」という全体講義を受け、その後、3つのグループに分かれて見学を行いました。見学先は、物性研究所国際超強磁場科学研究施設・宇宙線研究所・宇宙探査ミッションに搭載する科学観測装置の開発研究の地下実験室の3カ所でした。特に、地下実験室を見学したグループは、全身防護服を着用して見学を行い、最先端の研究施設を「肌で体感」することができたと思います。また、午後の大学見学は、東京都内の各大学に各自で見学に向かいました。見学先は、上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・日本大学・専修大学・東京医科大学・工学院大学・大妻女子大学の10大学です。この私大見学は、実際に公共交通機関を使って大学に向かうので、バスでの見学よりも大学の実際を体感できるものになったと思います。
このように、中高一貫コースでは、中学時代の校外理科研修の取り組みを踏まえながら、生徒の進路意識や学習意欲を高める行事に取り組んでいます。次年度以降も、5年生の東大・都内私大見学を継続しつつ、4年生については、現中学3年生がかずさDNA研究所と神田外語大学の見学を校外理科研修で行っているため、別の大学・研究所見学ができるよう準備を進めています。ご期待ください。

▲
【幼稚園】

■◆■認定こども園千葉明徳短期大学附属幼稚園 保育教諭 藍 柚佳■◆■
6月に入り水遊びの季節になりました。
年長児は園庭で水遊びをする中、週に1回JSSスイミングスクールへ行き、プール活動を行います。子どもたちの中には「楽しみ!」と嬉しそうに話す子や、「泳げない…」「怖い」と緊張する子など、様々な姿が見られました。
子どもたちにとって初めての活動となるため、どのようなことをするのかイメージが持てるように、昨年撮影したJSSでの動画を見せ、不安な気持ちを少しでも取り除くようにしました。
初回は準備体操から始まり、自分で水を身体にかけることからスタートしました。プール内では壁を伝ってカニ歩きをしたり、滑り台を滑ったりと、プールが初めての子も楽しめる活動がいっぱいでした。入水後の子どもたちは、「楽しかった!」「次のプールが楽しみ」と、たくさんの笑顔で溢れていました。スイミングスクールの指導コーチや監視職員には、「こんにちは!」「ありがとうございました!」と元気に挨拶をする子どもたちの姿も見られました。日々、挨拶を大切にしていて、年長児らしい様子が見られました。
また、この活動は遠足と同様、園外に出ることで地域交流や交通ルールの指導も同時に行われています。道中には交番もあり、警察の方が安全に横断歩道を渡れるように協力してくれています。
子どもたちも徐々に場に慣れてきましたが、今後も子どもの様子をしっかりと見て、JSSスイミングスクールの指導コーチや監視職員と協力し、安全管理を徹底して、子どもも大人も楽しいと思えるような活動にしていきたいです。

▲
【やちまた】

■◆■明徳やちまたこども園 保育教諭 齋藤 夏季■◆■
今年度、0歳児もも組は2名のスタートでしたが、5月には3名の新入園児が加わり、5名となって元気に過ごしています。
4・5月は、こども園の生活に慣れるように、室内遊びをメインに過ごしてきました。室内では、それぞれ興味のある玩具に手を伸ばして遊んだり、保育者との関わりを楽しんだりする姿が見られました。クラスからもっと広い場所に移動して、みんなの部屋ではのびのびとハイハイしたり、ステージを登ったり下りたりして、身体を動かして楽しんでいます。
こども園の生活にも慣れてきた6月。ハイハイや歩行が上手な子が増えてきたため、戸外デビューをして、広くて楽しい外へ!テラスから初めて降りる際には、おそるおそる地面に手を伸ばしていましたが、保育者の声かけで地面に降り立つと、ニコッと満面の笑顔♪そこからは、自分の好きな場所に行き、それぞれ探索を楽しんでいました。
これから暑い日がどんどん増えていくと思いますが、戸外へ出られる日は、水遊びも含めて、子どもたちとともに沢山体を動かして、様々な発見を楽しんでいこうと思います。

▲
【浜野】

■◆■明徳浜野駅保育園 保育士 坂口 聡美■◆■
今、本園では毎年恒例の蚕の飼育、カブトムシの飼育、そしてプランターでの野菜栽培を行っています。
蚕は毎年5月に農業会館から2齢幼虫を譲って頂いています。今年はいつもよりかなり多く、数えてみたらなんと320匹!そしてそのほとんどが繭になりました。繭は大事に保管され、保護者の手作りで卒園式につけるコサージュへと変身します。 繭になるまでの約2週間、桑の葉を大量に消費するので職員たちは毎年、葉っぱ集めに奔走します。今年も地域の方々からたくさんの桑の葉を頂くことができました。お礼として、ご協力頂いた皆様にもコサージュをお届けしようと思っています。
以上児クラスは主に蚕の飼育をしていますが、未満児クラスはカブトムシの飼育を行っています。去年のカブトムシが産んだ卵を採取し、幼虫からさなぎ、成虫となるまで毎日のように観察し、土を湿らせたりするお世話をしてくれました。ペーパーの芯を使った人工蛹室でさなぎを育てたので、変化していく姿を詳しく見られて、より興味津々な様子です。図鑑やカブトムシの本と見比べて「一緒だよ~」と保育者や迎えに来た保護者に伝えています。ちょっとしたカブトムシ博士がたくさんいますよ♪
プランターの野菜は、今年初チャレンジのきゅうりが大豊作!野菜が苦手な子どもたちも、「今日のサラダはみんなで育てたお野菜が入っているよ」と言うと、「美味しい~」と食べられます。なぜなら、それぞれが植えた苗に名前を付けるほど愛情がこもっているからです。「ぴーこ」「とまこ」「なすお」、そしてきゅうりには「つよし」!名前の通り、強風や大雨にも負けずスクスク育っています。 園庭の無い小さな園ですが、工夫して自然に触れられる環境を整え、子どもたちの「?」の種を育てていきたいと思います。

▲
【本八幡】
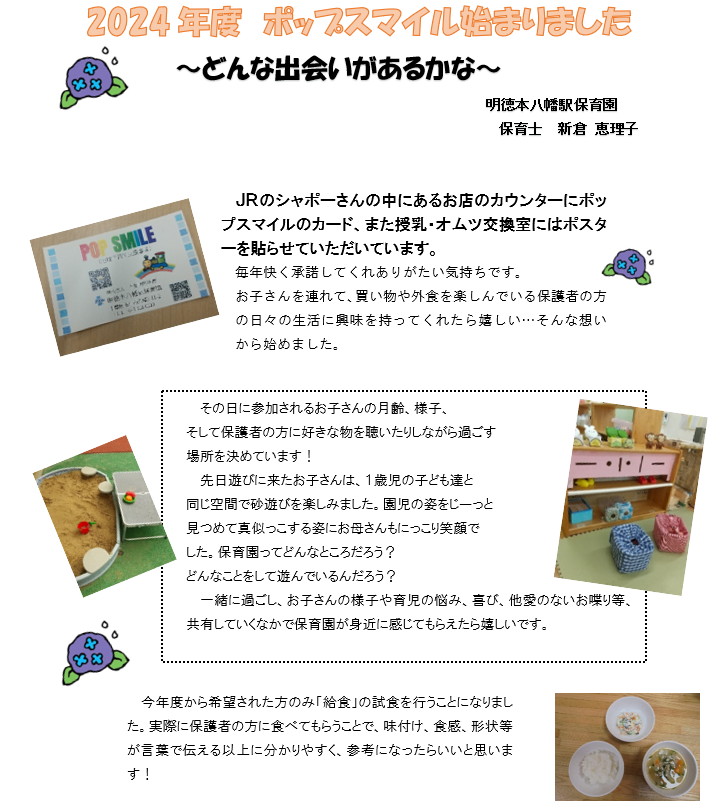
▲

■◆■千葉明徳中学校 教諭 松田 真生子■◆■
6月12日(水)〜6月14日(金)、中学2学年は初めての宿泊行事である林間学校へ行ってきました。
事前に5月のうちから3回にわたって事前学習を行い、主な来訪先である足尾銅山と尾瀬ヶ原について、歴史や自然保全の意義を少しは理解してもらえたのではないかと思います。
1日目は足尾銅山の見学および植林体験を行いました。銅山見学ではトロッコに乗ったり、坑道を歩きながら展示を見学しました。暗くひんやりした坑道内には当時の採掘作業の様子がリアルに再現されており、かなりの重労働であったことが、生徒たちにもよくわかったようです。植林体験では、公害により失われた自然を取り戻す作業として、1人1本、木の苗を植えました。
2日目は本州最大の湿原である尾瀬ヶ原のハイキングに出かけました。今年度は大多数の中2生が、15km以上を歩く一番長いコースにエントリーしました。最初は歩ききれるか不安がっている子が多かったですが、晴天に恵まれ、初夏の美しい景色を存分に楽しむことができたようです。ガイドさんの説明を聞きながら、尾瀬の自然を実際に見て学びました。最後は全員、自分の足で戻ってくることができ、とても達成感があったと話していました。
3日目は吹割の滝周辺の散策および原田農園でのさくらんぼ狩りを行いました。岩が侵食によって削られたところにできた滝は、えぐられた地面に水が落ちていくような、不思議で雄大な光景をつくっていました。さくらんぼ狩りでは、生徒たちがまるで宝探しのように、赤い実を探して楽しそうに食べていました。
全日通して天候に恵まれ、生徒たちが楽しそうにしていたのが印象に残っています。学友と長い時間を共に過ごし、普段の生活ではできない経験をたくさん味わったと思います。共同生活の難しさや、自分に足りないものも見えたと思いますので、これからの学校生活に活かしてくれることを願っています。

【短大】

■◆■千葉明徳短期大学 准教授 中嶋 一郎■◆■
2024年5月26日(日)、千葉県総合スポーツセンター陸上競技場で毎年開催されている千葉県障がい者スポーツ大会に、本学の1年生84名と2年生2名、計86名がボランティアとして参加しました。
本学では「体験から学ぶ」という学習方法を重視しており、この大会も授業の一環として位置付けられています。学生たちは、さまざまな特徴を持つ人たちとの関わりを通じて、自己理解、他者理解、障がいの理解を深めることを目的に、毎年1年生がボランティアとして参加しています。
大会では、50m走、100m走、200m走、400m走などのトラック競技、立幅跳び、走幅跳びなどの跳躍競技、砲丸投げ、ジャベリックスローなどの投てき競技が行われました。学生たちは、競技への誘導、種目ごとの記録の掲示、受付業務などの役割に分かれてボランティア活動を行いました。
当日は5月とは思えないような暑さ(最高気温25.2℃)で、夏のような日差しが降り注ぐ中、競技者たちは日ごろの努力を結果に結びつけようと一生懸命にスポーツに取り組んでいました。学生たちも、ボランティアを通じて選手たちと関わる中で、多くの変化が見られました。
初めての経験に不安を抱いていた学生も少なくありませんでしたが、真剣に競技に打ち込む選手の姿や、競技中に必要なサポートをする人々、そして競技者を応援する人々の姿に感動し、実際にサポートを行う中で不安は次第に消えていきました。
また、学生たちは後日の振り返りの際に、国際生活機能分類に基づく障がいの理解が深まったことを示しました。今回のボランティア活動を通じて、学生たちは「障がい」に対する概念を見直し、理解を深めることができました。
来年度もこの大会を通じて、さまざまな人と関わり、学生たちが自己および他者の理解を深める機会となることを期待しています。

【高校】

■◆■千葉明徳高等学校 教諭 林 直樹■◆■
高等学校中高一貫コースでは、今年度より6月上旬に「一貫進路の日」を設定しました。
この進路の日は、昨年度まで一貫コースの「全校遠足」で実施していたものを、別日程に再設定したものです。この行事は、最先端の研究所や首都圏の大学見学を通して、文系・理系問わず、生徒の進路意識を高めることが目的です。
今年度は、高校1年生(4年生)が、かずさDNA研究所(午前)と神田外語大学(午後)に、高校2年生(5年生)が、東京大学柏キャンパス(午前)と生徒各自の都内私大見学(午後)にそれぞれ向かいました。
4年生が訪れたかずさDNA研究所では、ブロッコリーからDNAを抽出する実験を体験し、研究所内の見学も行いました。また、神田外語大学では、大学教員から「大学で外国語を学ぶ意味」についての講義を受け、大学生によるキャンパス見学を行いました。中学時代のフィールドワーク中心だった「校外理科研修」からの大きな変化を体験できたと思います。
一方、5年生が訪れた東大柏キャンパスでは、最初に大学教員による「海洋学者という進路を選んで」という全体講義を受け、その後、3つのグループに分かれて見学を行いました。見学先は、物性研究所国際超強磁場科学研究施設・宇宙線研究所・宇宙探査ミッションに搭載する科学観測装置の開発研究の地下実験室の3カ所でした。特に、地下実験室を見学したグループは、全身防護服を着用して見学を行い、最先端の研究施設を「肌で体感」することができたと思います。また、午後の大学見学は、東京都内の各大学に各自で見学に向かいました。見学先は、上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・日本大学・専修大学・東京医科大学・工学院大学・大妻女子大学の10大学です。この私大見学は、実際に公共交通機関を使って大学に向かうので、バスでの見学よりも大学の実際を体感できるものになったと思います。
このように、中高一貫コースでは、中学時代の校外理科研修の取り組みを踏まえながら、生徒の進路意識や学習意欲を高める行事に取り組んでいます。次年度以降も、5年生の東大・都内私大見学を継続しつつ、4年生については、現中学3年生がかずさDNA研究所と神田外語大学の見学を校外理科研修で行っているため、別の大学・研究所見学ができるよう準備を進めています。ご期待ください。

【幼稚園】

■◆■認定こども園千葉明徳短期大学附属幼稚園 保育教諭 藍 柚佳■◆■
6月に入り水遊びの季節になりました。
年長児は園庭で水遊びをする中、週に1回JSSスイミングスクールへ行き、プール活動を行います。子どもたちの中には「楽しみ!」と嬉しそうに話す子や、「泳げない…」「怖い」と緊張する子など、様々な姿が見られました。
子どもたちにとって初めての活動となるため、どのようなことをするのかイメージが持てるように、昨年撮影したJSSでの動画を見せ、不安な気持ちを少しでも取り除くようにしました。
初回は準備体操から始まり、自分で水を身体にかけることからスタートしました。プール内では壁を伝ってカニ歩きをしたり、滑り台を滑ったりと、プールが初めての子も楽しめる活動がいっぱいでした。入水後の子どもたちは、「楽しかった!」「次のプールが楽しみ」と、たくさんの笑顔で溢れていました。スイミングスクールの指導コーチや監視職員には、「こんにちは!」「ありがとうございました!」と元気に挨拶をする子どもたちの姿も見られました。日々、挨拶を大切にしていて、年長児らしい様子が見られました。
また、この活動は遠足と同様、園外に出ることで地域交流や交通ルールの指導も同時に行われています。道中には交番もあり、警察の方が安全に横断歩道を渡れるように協力してくれています。
子どもたちも徐々に場に慣れてきましたが、今後も子どもの様子をしっかりと見て、JSSスイミングスクールの指導コーチや監視職員と協力し、安全管理を徹底して、子どもも大人も楽しいと思えるような活動にしていきたいです。

【やちまた】

■◆■明徳やちまたこども園 保育教諭 齋藤 夏季■◆■
今年度、0歳児もも組は2名のスタートでしたが、5月には3名の新入園児が加わり、5名となって元気に過ごしています。
4・5月は、こども園の生活に慣れるように、室内遊びをメインに過ごしてきました。室内では、それぞれ興味のある玩具に手を伸ばして遊んだり、保育者との関わりを楽しんだりする姿が見られました。クラスからもっと広い場所に移動して、みんなの部屋ではのびのびとハイハイしたり、ステージを登ったり下りたりして、身体を動かして楽しんでいます。
こども園の生活にも慣れてきた6月。ハイハイや歩行が上手な子が増えてきたため、戸外デビューをして、広くて楽しい外へ!テラスから初めて降りる際には、おそるおそる地面に手を伸ばしていましたが、保育者の声かけで地面に降り立つと、ニコッと満面の笑顔♪そこからは、自分の好きな場所に行き、それぞれ探索を楽しんでいました。
これから暑い日がどんどん増えていくと思いますが、戸外へ出られる日は、水遊びも含めて、子どもたちとともに沢山体を動かして、様々な発見を楽しんでいこうと思います。

【浜野】

■◆■明徳浜野駅保育園 保育士 坂口 聡美■◆■
今、本園では毎年恒例の蚕の飼育、カブトムシの飼育、そしてプランターでの野菜栽培を行っています。
蚕は毎年5月に農業会館から2齢幼虫を譲って頂いています。今年はいつもよりかなり多く、数えてみたらなんと320匹!そしてそのほとんどが繭になりました。繭は大事に保管され、保護者の手作りで卒園式につけるコサージュへと変身します。 繭になるまでの約2週間、桑の葉を大量に消費するので職員たちは毎年、葉っぱ集めに奔走します。今年も地域の方々からたくさんの桑の葉を頂くことができました。お礼として、ご協力頂いた皆様にもコサージュをお届けしようと思っています。
以上児クラスは主に蚕の飼育をしていますが、未満児クラスはカブトムシの飼育を行っています。去年のカブトムシが産んだ卵を採取し、幼虫からさなぎ、成虫となるまで毎日のように観察し、土を湿らせたりするお世話をしてくれました。ペーパーの芯を使った人工蛹室でさなぎを育てたので、変化していく姿を詳しく見られて、より興味津々な様子です。図鑑やカブトムシの本と見比べて「一緒だよ~」と保育者や迎えに来た保護者に伝えています。ちょっとしたカブトムシ博士がたくさんいますよ♪
プランターの野菜は、今年初チャレンジのきゅうりが大豊作!野菜が苦手な子どもたちも、「今日のサラダはみんなで育てたお野菜が入っているよ」と言うと、「美味しい~」と食べられます。なぜなら、それぞれが植えた苗に名前を付けるほど愛情がこもっているからです。「ぴーこ」「とまこ」「なすお」、そしてきゅうりには「つよし」!名前の通り、強風や大雨にも負けずスクスク育っています。 園庭の無い小さな園ですが、工夫して自然に触れられる環境を整え、子どもたちの「?」の種を育てていきたいと思います。

【本八幡】