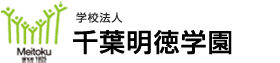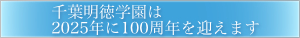学園ニュース
学園ニュース 2024年11月号(289号)
【短大】

■◆■千葉明徳短期大学 講師 井上 裕美子■◆■
2024年11月16日(土)、第21回木更津こどもまつりのボランティアスタッフとして明徳短期大学学生の有志が参加しました。
木更津こどもまつりは、地域住民、企業、学校、ボランティア団体など、多くの人々の協働によって実現する、地域活性化と子育て支援を目的とした、歴史あるイベントです。この木更津こどもまつりに、明徳短期大学はボランティアとして15年前から携わっています。昨年担当していた古賀拓也講師に誘われ、井上も担当することになりました。今年初めて担当し、有志の短期大学生が生き生きと参加していた姿、地域を活性化させたいという熱い想いを持って子育て支援をしている方々の姿を見て、教員として学ぶことも多く、これから地域貢献としてできることを改めて考えた日でした。そのときに肌で感じたことを学園ニュースにてお伝えしたいと思います。
本学学生は、まつりの主要企画である「ももたろう」をテーマにしたシールラリーの運営補助を行いました。 「ももたろう」の仲間の犬やさるになりきり、シールラリーを楽しむ子どもたちから「きび団子」をもらい、仲間になった証としてシールを貼るという役割を担当しました。学生たちは、指定された範囲の場所を歩いたりしながら、ももたろうのお面を付けたこどもたちに「仲間にしてほしい」「きびだんごがほしいな。一緒に鬼を倒そうね」 と声をかけるなど、保護者やこどもへ積極的に関わっていました。学生たちは、子どもたちへの対応をする中で、地域の人たちが「あれ、〇〇君だよね。大きくなったね」と久しぶり に会ったこどもたちに話しかけたり、地域の人たち同士が知り合いで出展者もボランティア参加者も、お客側も気軽に声をかけている様子に感銘を受けていました。
学生から「『こどもまつり』という名前なだけあって、本当に子どもたちが楽しめるようなお祭りだと思いました。ボランティアに参加して人との繋がりは本当に素敵だなと思いましたし、何よりもこどもたちの笑顔がたくさん見られたことが今回ボランティアに参加してよかったなと思いました。」という感想をもらいました。
他にも「地域でこどものための祭りを開催することによって、大人同士も地域を守ろうという気持ちが高め合えるのかなと思いました。」「こどもとの関わりだけではなく、地域の人達との関わりを持つことによってさらに関わりを増やしていくことができ、地域の人達との関わりの影響でできた祭りなのではないかと思いました。」等、参加していた学生たちは、参加者みんなが知り合いで、参加した人たちがこどもたちのことを中心にまつりを創り上げる、その一体感が素敵だと口々に話していました。ボランティア参加学生の多くが2年生であり、こどもたちが楽しむためには、多岐にわたる配慮と準備が必要であり、それには多くの時間もかかることを理解していました。運営委員が行うまつりの準備や当日の運営の大変さも想像をしながら、この熱量で毎年実施している木更津地域の方たちを尊敬の目で見 つつ、自分たちも参加者として大いに楽しんでいたようです。
学生の「地域のお祭りに参加することは初めてではないけど、ボランティアとして参加するのは初めてで、新しい経験をたくさんできました。子ども達の笑顔が何よりの宝だなと心から感じました。」という感想が、活動の充実度を物語っていると感じています。 利益のためではなく、誰かのために何かをすることの意義を深く理解し、「自分自身ももっと誰かのためになるようなことをしたい」という前向きな姿勢も育まれました。
今回のボランティア活動を通して、学生たちは、地域社会への貢献の大切さ、人との繋がり、そして社会参加の喜びを学んでいました。地域一体となって子どもに様々な経験を提供する機会が確かに減っている昨今、「また明徳短期大学の学生にお願いしたい」と言ってもらえ、地域と15年も繋がっていることは本学の大きな財産であると思います。まつり に参画することにより、こどもを支える環境を考える、地域貢献を考える一助として貴重な経験を頂きました。教員として、木更津こどもまつり実行委員の皆様とこれまでの明徳短期大学の卒業生が繋いできた経験のバトンを、これからの明徳学生へ伝え、次世代の子育て支援について改めて考えていきたいと思います。

▲
【中学校】

■◆■千葉明徳中学校 教諭 川村 玄季■◆■
コロナ禍を抜け、多くの行事を経験してきた12期生。
ところが今回は、マイコプラズマ感染症による学年閉鎖が直前に行われました。学年団は宿泊行事直前に生徒達と会えないことに不安を抱きつつも、結団式を経て奈良・京都への修学旅行に向かうことができました。
1~2日目は奈良で、古都の面影を辿りました。特に明日香地区サイクリングが印象的で、一見何もない原風景を巡っているように見えるものの、かつてそこに都が広がっていたことを想起させる史跡が多くあり、人の営みが時と共に行き過ぎてしまうことの無常さを感じさせられました。
3日目は京都班別自由研修。伏見稲荷大社、清水寺、嵐山…と名所を訪れる生徒が多かったようです。京都といえば何を思い浮かべますか?私は真っ先に、オオクワガタ&オオサンショウウオを思い浮かべました。登山は楽しさゆえに帰れなくなりそうだったため、京都水族館を訪れることにしました。入ってすぐオオサンショウウオまみれ...天国でした。ずっとここに居たい!と後ろ髪を引かれながらも次の目的地に。今は高3の受験シーズン。学業といえば菅原道真公を祀る北野天満宮!...ではなく、日本書紀の編者で、日本最初の学者とも言われる舎人親王を祀る藤森神社を参拝しました。静かで心地よい空間で、受験生の健闘と合格をお祈りしてきました。その後生徒を探すも全く会えず、しばらくして宿方面へ。ここで事態が急変。万全を期しての修学旅行だったはずが、多数の生徒が体調不良になりました。原因はインフルエンザ。この日は遅くまで教員も慌ただしく、生徒達も察してくれたのか翌日の荷物準備まで協力し、スムーズにこなしてくれました。
前日のことで不安はありつつも、最終日へ。まずは、一般公開されていない宋仙寺で、滅多に体験できない座禅に挑戦。20分間の体験でしたが、何も考えないようにすることを考えてしまって、無の境地は程遠いと感じました。生徒達も真剣に取り組んでいて、中には警策で喝を入れてもらう様子も見られました。ご住職様からありがたいお話をいただき、憑き物が落ちたような感覚でお寺を後にしました。その後は三十三間堂を訪れ、大量の仏像を目の当たりに。一つ一つ顔が違うらしいのですが、全く気がつきませんでした。
新幹線で帰路に就く中、今回の旅をぼんやりと振り返っていました。改めて日本の歴史や文化等に触れ、日本の良さに気づけたこと。修学旅行を通じ、普段見えない生徒達の側面を見ながら、多くの話を一緒になってできたこと。何より、不測の事態が発生したにも関わらず何とか旅程を乗り切れたのは、多くの方々の尽力やチームワークがあり、保護者の皆様方にも多くの面でご協力をいただいたおかげであったと実感しました。再び学年閉鎖になったことは心苦しいばかりですが、この状況を抜けた先で前向きに進んでいけるよう祈るばかりです。

▲
【浜野】

■◆■明徳浜野駅保育園 保育士 坂口 聡美■◆■
11月2日(土)に卒退園児とその保護者を対象とした「めいとくのつどい」を行いました。
この行事は、子どもたちの成長を20歳まで追いかけよう!という「めいとく20年プロジェクト」として、毎年実施しているものです。
コロナ禍で中止していた期間が続き、4年振りの実施となった昨年度は、職員も張り切りすぎて(⁉)内容も盛りだくさんとなり、ちょっと慌ただしさがあったかな…という反省が出るほどでした。それを受けて、今年度はゆったりとした空間の中で楽しい時間を過ごしてもらえるようなコーナー作りを心がけ準備をしていき、当日は各コーナーの職員も交代で園内を回り、保護者の方や子ども達とゆっくりと話したり一緒に遊んだりすることができました。
この日は、あいにくの雨模様でしたが、「雨で練習が中止になったから来たよ!」と、当日の飛び入り参加の中学生もいて久しぶりの再会を喜び合いました。
ペン1本で描けるコースター作りは、職員や園長との話に花が咲き保護者の方で席が埋まってしまったり、ゲームコーナーでは親子や先輩後輩でも一緒に楽しむ姿があったりして、みんながキラキラと輝いていました。最後のクイズ大会では賞品の「保育園体験チケット」をかけて、小学生も中学生も大興奮!昔に返ったように大喜びしている姿をみて微笑ましかったです。
子ども達といっても、もう来年から社会人だったり、高校生もいたりするのですが、「先生!内定もらったよ!」と意気揚々と報告してくれたり「将来は理学療法士になりたいから、専門学校か大学かで迷っているの」など、自身の将来像を語ってくれたりしてくれて、本当にこの会を続けてきて良かったな、と感慨深いものがありました。
次回も保護者や子ども達を「おかえりなさい♪」と暖かく出迎え、楽しいひとときを一緒に過ごしていきたいと思います。

▲
【高校】

■◆■千葉明徳高等学校 教諭 太田 和広■◆■
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により数年間中止となっていたシンガポールマレーシア研修が再開され、先発の9,10、11、12組が10月21日(月)から25日(金)まで、後発の3、4、5,6,7,8組は10月22(火)から26日(土)まで、3泊5日で実施しました。
当初は、新型コロナウイルス感染症拡大前の経験からシンガポールを経由してのマレーシア入国に時間がかかる事を予想しておりましたが、シンガポールマレーシア両国の出入国システムもデジタル化されており、予定していた時程より大幅に手続きがスムーズになり研修初日のマレーシアの宿舎到着も以前より大幅に早く到着することができました。
研修2日目はマレーシアの現地の学校と村を訪問しました。学校では生徒とマレーシアのゲームなどを通じて交流しました。村では現地のお宅にお邪魔し、カレーを食べて現地の民族衣装を着るなど日本とは違う文化を経験してきました。最初は硬い表情だった本校の生徒達も現地校の生徒と共に過ごす時間が長くなるにつれてお互いに打ち解けあい、最後は別れ惜しく記念写真を撮影するなどしていました。研修後は慌ただしくシンガポールへの再入国を済ませ、夜半にシンガポールの宿舎へ到着しました。研修3日目はシンガポール大学の学生とのB&Sプログラムでシンガポール市内の班別研修を実施しました。生徒達はシンガポールでの班別行動計画を文化祭、体育祭、中間考査と慌ただしい日程の中でよくまとめ上げて、研修当日はシンガポール大の学生と英語を通して、おすすめのお土産や昼食場所を聞いたりするなど頑張っておりました。研修後は、前日の学校訪問や村訪問と同様にシンガポール大の学生と別れ惜しく一緒に記念写真を撮っている生徒が多数いました。
研修最終日の午前中は市内の戦争平和記念碑やマーライオイン公園など市内の主だった施設を見学し、午後はユニバーサルスタジオシンガポールの見学を行いました。生徒達はここまでの慌ただしい日程や熱帯の厳しい環境の中でも最後まで研修旅行を満喫しているようでした。

▲
【やちまた】

■◆■明徳やちまたこども園 保育教諭 井合 萌々佳■◆■
さくら組がスタートしてから半年が過ぎました。<br> 4月当初は緊張からか、何をして良いのか分からず、担任と一緒に遊ぶことで安心していた子も、今では友だちと一緒に「これやろう」と声をかけ、誘い合って遊ぶ姿が見られるようになりました。また、アスレチックや築山など、友だちが挑戦している姿に刺激を受け、自分もやってみようと頑張る子も増えてきています。
秋になり、収穫の時期がやってきました。今年も園庭のみかんや柿が豊作!子どもたちも喜んで食べていました。先日は、お世話になっている畑で枝豆の収穫体験をさせてもらいました。みんなで「うんとこしょ、どっこいしょ」とかけ声を出し“大きなかぶ”のように楽しみながら抜いたのですが、取れた枝豆を見て「うわぁ」と歓声が!!抜くのに夢中で気が付かなかったようですが、あまりにもたくさんの豆がついていたのでびっくりしたようです。
その後、枝豆を茹でて食べました。茹でている時から「いい匂い」と匂いを嗅ぎ、今か今かとそわそわ・・・。食べてみると、「おいしい」と何回もおかわりをするほど人気でした。
別の日には、さつまいもの収穫をしました。掘っても掘ってもなかなか抜けないさつまいもに大苦戦でしたが、それでも諦めず、時には「こっちを手伝って」と周りに声を掛けみんなで協力し収穫する姿もありました。また、何かが出入りしたような小さな穴に「トンネルがある」と興味津々に覗き込む一幕もあり、さつまいもを掘りながら新たな楽しみに目を向ける様子もありました。
さつまいもは甘くなるまで1か月。食べるのはもう少しさきになりますが、みんなで調理をして味わいたいと思います。

▲
【幼稚園】

■◆■認定こども園千葉明徳短期大学附属幼稚園 保育教諭 菅谷 帆乃香■◆■
2歳児クラスでは、自然が豊かな学園内を散歩する機会が増えてきています。<br> 少し離れた3~5歳児の園舎に行くのは2歳児にとって少し長い道のりです。しかし、子ども達にとっては長い道も、宝物がいっぱいの楽しい時間になるようです。<br> みかんの木、さつまいも畑、おしろい花、柿の木など、普段1,2歳児の園舎では見ることのない自然に興味津々の子ども達。何度も通ることで、どこになにがあるのかがわかってきている子ども達は、「今日のみかんはまだ緑だよ」「柿が落ちてるね」「このお花は手がピンクになるんだよ」と、自然を感じながら散歩をしていることがよくわかります。<br> 中でも一番の宝物がどんぐりです。たくさん落ちている場所では、自分たちでどんぐりを見つけて、お家の人へお土産にする!と張り切って探します。良いどんぐりを見つけた子ども達は、お散歩バッグの中にたくさんのどんぐりを入れて、大事に守りながらクラスの部屋まで持ち帰り、お家の人へキラキラの瞳でプレゼントする光景はとても素敵なものだと感じます。<br> たくさん拾ったどんぐりはお砂場でごっこ遊びに使用する子もいます。どんぐりをたくさんのせたどんぐりケーキ、どんぐりジュースは、子どもがこだわりながら飾り付けしたり、1歳児クラスの子にもプレゼントしたりして、友だちとの遊びを楽しみながら、秋を感じているのではないかと思いました。<br> これからも散歩や遊びの中で、様々な宝物を探していきたいと思います。

▲
【本八幡】

■◆■明徳本八幡駅保育園 保育士 藤代 桜香■◆■
保護者も参加型の行事であるおたのしみ会が行われました。
「どんぐりを探そう!」という子どもたちの声で散歩に行き、集めてきたどんぐりを使って親子でマラカスを作って遊びました。それぞれの家庭から持ち寄ったボトルにどんぐりを入れて。ボトルに丸シールやハロウィンのシールを貼って完成!作りながらも「どんぐりたくさん入れたい!」「どのシール貼る?」など親子で楽しそうな会話が聞こえてきました。
「どんぐりを探そう!」という子どもたちの声で散歩に行き、集めてきたどんぐりを使って親子でマラカスを作って遊びました。それぞれの家庭から持ち寄ったボトルにどんぐりを入れて。ボトルに丸シールやハロウィンのシールを貼って完成!作りながらも「どんぐりたくさん入れたい!」「どのシール貼る?」など親子で楽しそうな会話が聞こえてきました。完成したマラカスを使って演奏会。前にあるステージに見立てたマットの上や、パパ・ママの傍で、「どんぐりコロコロ」「おばけなんてないさ」「おもちゃのチャチャチャ」など歌に合わせてシャカシャカ鳴らしてみんなの笑顔がいっぱいでした!また、子どもたちが園で楽しんでいるパネルシアターや触れ合い遊びも親子で楽しみました。「一本橋」「にらめっこ」など大好きなパパ・ママと一緒に楽しんだことでいつもと違う環境でドキドキしていた子どもたちもにこにこ笑顔に!パパ・ママも子どもたちが楽しんでいる姿を見てとても嬉しそうでした!
おたのしみ会という形で親子一緒に遊ぶ時間を作ったことで子どもたちの成長を感じ、共有することができる有意義な時間になったと感じています。
▲
【法人事務局】

■◆■法人事務局 広報室■◆■
11月22日(金)に学校法人千葉明徳学園理事会が開催されました。以下のとおり報告します。
-理事会-
理事8名出席、監事2名参加のもと、10時00分から本館1階会議室にて行われ、いずれの議案も承認されました。
■議事内容
第1議案 2025年度所属長人事について
第2議案 労働基準監督署指導監査における是正について
第3議案 学校法人千葉明徳学園超過勤務手当支給に関する規程の改定について
第4議案 第4議案 学校法人千葉明徳学園保育施設給与規則の改定について
第5議案 その他
■報告事項
1.学生・生徒・園児の募集状況について
2.評議員の選任について
3.その他
▲

■◆■千葉明徳短期大学 講師 井上 裕美子■◆■
2024年11月16日(土)、第21回木更津こどもまつりのボランティアスタッフとして明徳短期大学学生の有志が参加しました。
木更津こどもまつりは、地域住民、企業、学校、ボランティア団体など、多くの人々の協働によって実現する、地域活性化と子育て支援を目的とした、歴史あるイベントです。この木更津こどもまつりに、明徳短期大学はボランティアとして15年前から携わっています。昨年担当していた古賀拓也講師に誘われ、井上も担当することになりました。今年初めて担当し、有志の短期大学生が生き生きと参加していた姿、地域を活性化させたいという熱い想いを持って子育て支援をしている方々の姿を見て、教員として学ぶことも多く、これから地域貢献としてできることを改めて考えた日でした。そのときに肌で感じたことを学園ニュースにてお伝えしたいと思います。
本学学生は、まつりの主要企画である「ももたろう」をテーマにしたシールラリーの運営補助を行いました。 「ももたろう」の仲間の犬やさるになりきり、シールラリーを楽しむ子どもたちから「きび団子」をもらい、仲間になった証としてシールを貼るという役割を担当しました。学生たちは、指定された範囲の場所を歩いたりしながら、ももたろうのお面を付けたこどもたちに「仲間にしてほしい」「きびだんごがほしいな。一緒に鬼を倒そうね」 と声をかけるなど、保護者やこどもへ積極的に関わっていました。学生たちは、子どもたちへの対応をする中で、地域の人たちが「あれ、〇〇君だよね。大きくなったね」と久しぶり に会ったこどもたちに話しかけたり、地域の人たち同士が知り合いで出展者もボランティア参加者も、お客側も気軽に声をかけている様子に感銘を受けていました。
学生から「『こどもまつり』という名前なだけあって、本当に子どもたちが楽しめるようなお祭りだと思いました。ボランティアに参加して人との繋がりは本当に素敵だなと思いましたし、何よりもこどもたちの笑顔がたくさん見られたことが今回ボランティアに参加してよかったなと思いました。」という感想をもらいました。
他にも「地域でこどものための祭りを開催することによって、大人同士も地域を守ろうという気持ちが高め合えるのかなと思いました。」「こどもとの関わりだけではなく、地域の人達との関わりを持つことによってさらに関わりを増やしていくことができ、地域の人達との関わりの影響でできた祭りなのではないかと思いました。」等、参加していた学生たちは、参加者みんなが知り合いで、参加した人たちがこどもたちのことを中心にまつりを創り上げる、その一体感が素敵だと口々に話していました。ボランティア参加学生の多くが2年生であり、こどもたちが楽しむためには、多岐にわたる配慮と準備が必要であり、それには多くの時間もかかることを理解していました。運営委員が行うまつりの準備や当日の運営の大変さも想像をしながら、この熱量で毎年実施している木更津地域の方たちを尊敬の目で見 つつ、自分たちも参加者として大いに楽しんでいたようです。
学生の「地域のお祭りに参加することは初めてではないけど、ボランティアとして参加するのは初めてで、新しい経験をたくさんできました。子ども達の笑顔が何よりの宝だなと心から感じました。」という感想が、活動の充実度を物語っていると感じています。 利益のためではなく、誰かのために何かをすることの意義を深く理解し、「自分自身ももっと誰かのためになるようなことをしたい」という前向きな姿勢も育まれました。
今回のボランティア活動を通して、学生たちは、地域社会への貢献の大切さ、人との繋がり、そして社会参加の喜びを学んでいました。地域一体となって子どもに様々な経験を提供する機会が確かに減っている昨今、「また明徳短期大学の学生にお願いしたい」と言ってもらえ、地域と15年も繋がっていることは本学の大きな財産であると思います。まつり に参画することにより、こどもを支える環境を考える、地域貢献を考える一助として貴重な経験を頂きました。教員として、木更津こどもまつり実行委員の皆様とこれまでの明徳短期大学の卒業生が繋いできた経験のバトンを、これからの明徳学生へ伝え、次世代の子育て支援について改めて考えていきたいと思います。

【中学校】

■◆■千葉明徳中学校 教諭 川村 玄季■◆■
コロナ禍を抜け、多くの行事を経験してきた12期生。
ところが今回は、マイコプラズマ感染症による学年閉鎖が直前に行われました。学年団は宿泊行事直前に生徒達と会えないことに不安を抱きつつも、結団式を経て奈良・京都への修学旅行に向かうことができました。
1~2日目は奈良で、古都の面影を辿りました。特に明日香地区サイクリングが印象的で、一見何もない原風景を巡っているように見えるものの、かつてそこに都が広がっていたことを想起させる史跡が多くあり、人の営みが時と共に行き過ぎてしまうことの無常さを感じさせられました。
3日目は京都班別自由研修。伏見稲荷大社、清水寺、嵐山…と名所を訪れる生徒が多かったようです。京都といえば何を思い浮かべますか?私は真っ先に、オオクワガタ&オオサンショウウオを思い浮かべました。登山は楽しさゆえに帰れなくなりそうだったため、京都水族館を訪れることにしました。入ってすぐオオサンショウウオまみれ...天国でした。ずっとここに居たい!と後ろ髪を引かれながらも次の目的地に。今は高3の受験シーズン。学業といえば菅原道真公を祀る北野天満宮!...ではなく、日本書紀の編者で、日本最初の学者とも言われる舎人親王を祀る藤森神社を参拝しました。静かで心地よい空間で、受験生の健闘と合格をお祈りしてきました。その後生徒を探すも全く会えず、しばらくして宿方面へ。ここで事態が急変。万全を期しての修学旅行だったはずが、多数の生徒が体調不良になりました。原因はインフルエンザ。この日は遅くまで教員も慌ただしく、生徒達も察してくれたのか翌日の荷物準備まで協力し、スムーズにこなしてくれました。
前日のことで不安はありつつも、最終日へ。まずは、一般公開されていない宋仙寺で、滅多に体験できない座禅に挑戦。20分間の体験でしたが、何も考えないようにすることを考えてしまって、無の境地は程遠いと感じました。生徒達も真剣に取り組んでいて、中には警策で喝を入れてもらう様子も見られました。ご住職様からありがたいお話をいただき、憑き物が落ちたような感覚でお寺を後にしました。その後は三十三間堂を訪れ、大量の仏像を目の当たりに。一つ一つ顔が違うらしいのですが、全く気がつきませんでした。
新幹線で帰路に就く中、今回の旅をぼんやりと振り返っていました。改めて日本の歴史や文化等に触れ、日本の良さに気づけたこと。修学旅行を通じ、普段見えない生徒達の側面を見ながら、多くの話を一緒になってできたこと。何より、不測の事態が発生したにも関わらず何とか旅程を乗り切れたのは、多くの方々の尽力やチームワークがあり、保護者の皆様方にも多くの面でご協力をいただいたおかげであったと実感しました。再び学年閉鎖になったことは心苦しいばかりですが、この状況を抜けた先で前向きに進んでいけるよう祈るばかりです。

【浜野】

■◆■明徳浜野駅保育園 保育士 坂口 聡美■◆■
11月2日(土)に卒退園児とその保護者を対象とした「めいとくのつどい」を行いました。
この行事は、子どもたちの成長を20歳まで追いかけよう!という「めいとく20年プロジェクト」として、毎年実施しているものです。
コロナ禍で中止していた期間が続き、4年振りの実施となった昨年度は、職員も張り切りすぎて(⁉)内容も盛りだくさんとなり、ちょっと慌ただしさがあったかな…という反省が出るほどでした。それを受けて、今年度はゆったりとした空間の中で楽しい時間を過ごしてもらえるようなコーナー作りを心がけ準備をしていき、当日は各コーナーの職員も交代で園内を回り、保護者の方や子ども達とゆっくりと話したり一緒に遊んだりすることができました。
この日は、あいにくの雨模様でしたが、「雨で練習が中止になったから来たよ!」と、当日の飛び入り参加の中学生もいて久しぶりの再会を喜び合いました。
ペン1本で描けるコースター作りは、職員や園長との話に花が咲き保護者の方で席が埋まってしまったり、ゲームコーナーでは親子や先輩後輩でも一緒に楽しむ姿があったりして、みんながキラキラと輝いていました。最後のクイズ大会では賞品の「保育園体験チケット」をかけて、小学生も中学生も大興奮!昔に返ったように大喜びしている姿をみて微笑ましかったです。
子ども達といっても、もう来年から社会人だったり、高校生もいたりするのですが、「先生!内定もらったよ!」と意気揚々と報告してくれたり「将来は理学療法士になりたいから、専門学校か大学かで迷っているの」など、自身の将来像を語ってくれたりしてくれて、本当にこの会を続けてきて良かったな、と感慨深いものがありました。
次回も保護者や子ども達を「おかえりなさい♪」と暖かく出迎え、楽しいひとときを一緒に過ごしていきたいと思います。

【高校】

■◆■千葉明徳高等学校 教諭 太田 和広■◆■
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により数年間中止となっていたシンガポールマレーシア研修が再開され、先発の9,10、11、12組が10月21日(月)から25日(金)まで、後発の3、4、5,6,7,8組は10月22(火)から26日(土)まで、3泊5日で実施しました。
当初は、新型コロナウイルス感染症拡大前の経験からシンガポールを経由してのマレーシア入国に時間がかかる事を予想しておりましたが、シンガポールマレーシア両国の出入国システムもデジタル化されており、予定していた時程より大幅に手続きがスムーズになり研修初日のマレーシアの宿舎到着も以前より大幅に早く到着することができました。
研修2日目はマレーシアの現地の学校と村を訪問しました。学校では生徒とマレーシアのゲームなどを通じて交流しました。村では現地のお宅にお邪魔し、カレーを食べて現地の民族衣装を着るなど日本とは違う文化を経験してきました。最初は硬い表情だった本校の生徒達も現地校の生徒と共に過ごす時間が長くなるにつれてお互いに打ち解けあい、最後は別れ惜しく記念写真を撮影するなどしていました。研修後は慌ただしくシンガポールへの再入国を済ませ、夜半にシンガポールの宿舎へ到着しました。研修3日目はシンガポール大学の学生とのB&Sプログラムでシンガポール市内の班別研修を実施しました。生徒達はシンガポールでの班別行動計画を文化祭、体育祭、中間考査と慌ただしい日程の中でよくまとめ上げて、研修当日はシンガポール大の学生と英語を通して、おすすめのお土産や昼食場所を聞いたりするなど頑張っておりました。研修後は、前日の学校訪問や村訪問と同様にシンガポール大の学生と別れ惜しく一緒に記念写真を撮っている生徒が多数いました。
研修最終日の午前中は市内の戦争平和記念碑やマーライオイン公園など市内の主だった施設を見学し、午後はユニバーサルスタジオシンガポールの見学を行いました。生徒達はここまでの慌ただしい日程や熱帯の厳しい環境の中でも最後まで研修旅行を満喫しているようでした。

【やちまた】

■◆■明徳やちまたこども園 保育教諭 井合 萌々佳■◆■
さくら組がスタートしてから半年が過ぎました。<br> 4月当初は緊張からか、何をして良いのか分からず、担任と一緒に遊ぶことで安心していた子も、今では友だちと一緒に「これやろう」と声をかけ、誘い合って遊ぶ姿が見られるようになりました。また、アスレチックや築山など、友だちが挑戦している姿に刺激を受け、自分もやってみようと頑張る子も増えてきています。
秋になり、収穫の時期がやってきました。今年も園庭のみかんや柿が豊作!子どもたちも喜んで食べていました。先日は、お世話になっている畑で枝豆の収穫体験をさせてもらいました。みんなで「うんとこしょ、どっこいしょ」とかけ声を出し“大きなかぶ”のように楽しみながら抜いたのですが、取れた枝豆を見て「うわぁ」と歓声が!!抜くのに夢中で気が付かなかったようですが、あまりにもたくさんの豆がついていたのでびっくりしたようです。
その後、枝豆を茹でて食べました。茹でている時から「いい匂い」と匂いを嗅ぎ、今か今かとそわそわ・・・。食べてみると、「おいしい」と何回もおかわりをするほど人気でした。
別の日には、さつまいもの収穫をしました。掘っても掘ってもなかなか抜けないさつまいもに大苦戦でしたが、それでも諦めず、時には「こっちを手伝って」と周りに声を掛けみんなで協力し収穫する姿もありました。また、何かが出入りしたような小さな穴に「トンネルがある」と興味津々に覗き込む一幕もあり、さつまいもを掘りながら新たな楽しみに目を向ける様子もありました。
さつまいもは甘くなるまで1か月。食べるのはもう少しさきになりますが、みんなで調理をして味わいたいと思います。

【幼稚園】

■◆■認定こども園千葉明徳短期大学附属幼稚園 保育教諭 菅谷 帆乃香■◆■
2歳児クラスでは、自然が豊かな学園内を散歩する機会が増えてきています。<br> 少し離れた3~5歳児の園舎に行くのは2歳児にとって少し長い道のりです。しかし、子ども達にとっては長い道も、宝物がいっぱいの楽しい時間になるようです。<br> みかんの木、さつまいも畑、おしろい花、柿の木など、普段1,2歳児の園舎では見ることのない自然に興味津々の子ども達。何度も通ることで、どこになにがあるのかがわかってきている子ども達は、「今日のみかんはまだ緑だよ」「柿が落ちてるね」「このお花は手がピンクになるんだよ」と、自然を感じながら散歩をしていることがよくわかります。<br> 中でも一番の宝物がどんぐりです。たくさん落ちている場所では、自分たちでどんぐりを見つけて、お家の人へお土産にする!と張り切って探します。良いどんぐりを見つけた子ども達は、お散歩バッグの中にたくさんのどんぐりを入れて、大事に守りながらクラスの部屋まで持ち帰り、お家の人へキラキラの瞳でプレゼントする光景はとても素敵なものだと感じます。<br> たくさん拾ったどんぐりはお砂場でごっこ遊びに使用する子もいます。どんぐりをたくさんのせたどんぐりケーキ、どんぐりジュースは、子どもがこだわりながら飾り付けしたり、1歳児クラスの子にもプレゼントしたりして、友だちとの遊びを楽しみながら、秋を感じているのではないかと思いました。<br> これからも散歩や遊びの中で、様々な宝物を探していきたいと思います。

【本八幡】

■◆■明徳本八幡駅保育園 保育士 藤代 桜香■◆■
保護者も参加型の行事であるおたのしみ会が行われました。
「どんぐりを探そう!」という子どもたちの声で散歩に行き、集めてきたどんぐりを使って親子でマラカスを作って遊びました。それぞれの家庭から持ち寄ったボトルにどんぐりを入れて。ボトルに丸シールやハロウィンのシールを貼って完成!作りながらも「どんぐりたくさん入れたい!」「どのシール貼る?」など親子で楽しそうな会話が聞こえてきました。
「どんぐりを探そう!」という子どもたちの声で散歩に行き、集めてきたどんぐりを使って親子でマラカスを作って遊びました。それぞれの家庭から持ち寄ったボトルにどんぐりを入れて。ボトルに丸シールやハロウィンのシールを貼って完成!作りながらも「どんぐりたくさん入れたい!」「どのシール貼る?」など親子で楽しそうな会話が聞こえてきました。完成したマラカスを使って演奏会。前にあるステージに見立てたマットの上や、パパ・ママの傍で、「どんぐりコロコロ」「おばけなんてないさ」「おもちゃのチャチャチャ」など歌に合わせてシャカシャカ鳴らしてみんなの笑顔がいっぱいでした!また、子どもたちが園で楽しんでいるパネルシアターや触れ合い遊びも親子で楽しみました。「一本橋」「にらめっこ」など大好きなパパ・ママと一緒に楽しんだことでいつもと違う環境でドキドキしていた子どもたちもにこにこ笑顔に!パパ・ママも子どもたちが楽しんでいる姿を見てとても嬉しそうでした!
おたのしみ会という形で親子一緒に遊ぶ時間を作ったことで子どもたちの成長を感じ、共有することができる有意義な時間になったと感じています。
▲
【法人事務局】

■◆■法人事務局 広報室■◆■
11月22日(金)に学校法人千葉明徳学園理事会が開催されました。以下のとおり報告します。
-理事会-
理事8名出席、監事2名参加のもと、10時00分から本館1階会議室にて行われ、いずれの議案も承認されました。
■議事内容
第1議案 2025年度所属長人事について
第2議案 労働基準監督署指導監査における是正について
第3議案 学校法人千葉明徳学園超過勤務手当支給に関する規程の改定について
第4議案 第4議案 学校法人千葉明徳学園保育施設給与規則の改定について
第5議案 その他
■報告事項
1.学生・生徒・園児の募集状況について
2.評議員の選任について
3.その他
▲